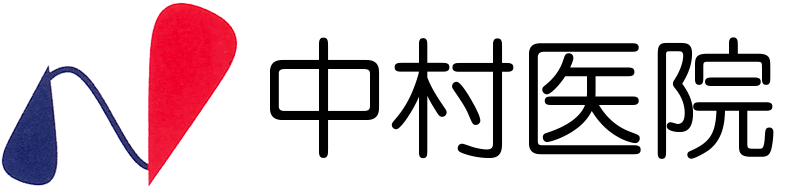作家の五木寛之さんが文藝春秋の読者から”羨ましい死に方”の原稿を募集されています。
コロナ禍、ウクライナ戦争等で私達の死生観が激変しています。
私にとって羨ましい死に方は、90歳の男性、亡くなる2時間前にビールを一口飲んで”ああ、うまい”と言って逝かれました。そして先日96歳で亡くなった私の父、急に食べられなくなってその翌日眠るように逝きました。
私達はいかに死ぬべきか?どうやったら安らかに死ねるのか?自分の中で死への物語を作ることが必要になると五木さんは言っています。
今、私達が死に直面するとき、最近はほぼ日常的にデジタルが登場します。
例えば、末期癌の患者さんの余命を予測するのは非常に難しい。聴診・触診など理学的所見を総合的に把握してから判断しますが、それでもはずれることも多いのです。そして告知するときに必要な大きな大きなエネルギー、患者さんの悲嘆に限りなく寄り添う必要があるのです。でも今は、電子カルテを見ながら、淡々と数字で死期を割り出します。
晩年にさしかかると、老人ホームに”入るか””入らないか”延命治療を”する”か”しない”かなど、死に至るまで0か1かのデジタル的な選択を迫られ、マニュアルに沿った処理を迫られる場面が増えます。死が間近に迫る深刻な状況でも白か黒かとなり、死が事務処理になっていく。羨ましい死に方はだんだん遠くなっていくのかもしれません。
さて、父が亡くなったとき、我が家の宗教は何?という感じで全く知りませんでした。宗教は人々を死の恐怖から救済することに特徴があり、平安後期から鎌倉時代に入ると法然や道元、日蓮などのリーダーたちが次々と比叡山を下り、民衆に布教して仏教を広めていきます。
羨ましい死に方はやはり、安らかな死に方をするということなのです。法然上人は摂取不捨を唱えて表れました。
全ての仏がつれなく過ぎ去っても、阿弥陀如来だけはあなたを捨てずに救う。十悪五逆をつくした悪人も”南無阿弥陀仏”さえ唱えれば、阿弥陀様は極楽浄土に導いてくださると説いたことで、浄土宗は爆発的な人気を博しました。宗教には物語を人々に信じ込ませるだけの絶大な力があるのです。
本日60代後半の女性、大腸癌で余命3ヶ月と宣言された方の往診をさせて頂きました。少々プレッシャーを感じながらの初対面でしたが、麻薬で痛みのコントロールができていて、驚くほど安らかに過ごされていました。お話しさせて頂いて、”死への物語”の確固たるものをお持ちなのだと教えて頂くことが多かったです。
自分だったらこんなに穏やかでいられるのだろうか。人も羨む生を最後まで生きていきたい、改めて思っています。そして愛も。人も羨むような愛を続けていくのも難しいのです。
To die peacefully, we need to solidity our own stories towards death in our minds.