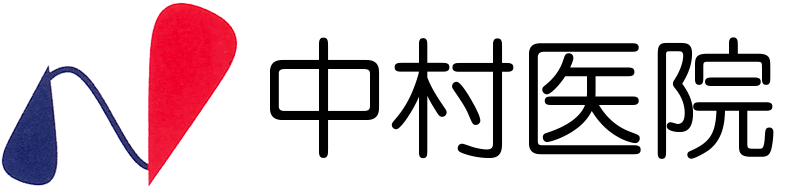人々にはそれぞれの人生がある。名門の武士として生まれるも突如23歳で出家した佐藤義清、出家後西行法師となり歌人としても活躍しました。

代表的な2首から、まず“身を捨つる人はまことに捨つるかは 捨てぬ人こそ捨つるなりけれ” 出家して身を捨てた人は本当に人生を捨てたのでしょうか。いえ俗世のしがらみに囚われた己を捨てられない人こそ、己の人生を捨てているのです。
そして73歳で息を引き取りましたが、生前に残した1首、私も理想的な最期と思っている大往生です。“願わくは花の下にて春死なん その如月の望月の頃” 願うことなら旧暦2月15日の満月の頃、満開の桜の下で死のう。
そして西行法師は、自ら望んだ日のわずか1日遅れで死んだのです。このことに当時の人々は驚嘆したと伝えられています。
さて、これに対して江戸時代の有名な歌人 小林一茶が亡くなる1年前に詠んだ句です。“花の影 寝まじ未来が恐ろしき” 未来とは仏教用語で死後のことを指しています。一茶は西行法師の和歌を踏まえつつ、全く逆のことを言っているのです。桜の花の影で眠ったらそのまま死んでしまうから、うかうか眠れないというのです。

死を恐れない西行の潔さと比べると、“死ぬのはこわい、死にたくない”と本音を吐いて、なんとも無様であり往生際が悪いのですが、自分を飾らずとても正直、それが一茶なのです。
今月号の文藝春秋で、小林一茶「死ぬのが恐い」往生際 大谷弘至氏からの記事です。サブタイトルは「母との死別、娘の夭折、二度の脳梗塞、なぜ辞世の句を遺さなかったのか」です。
代表的な句“雀の子そこのけそこのけお馬が通る” なんとも素朴ですよね。かつての日本は歌人たちは辞世の句を遺しています。例えば、松尾芭蕉は“旅に病んで夢は枯野をかけめぐる”

でも一茶は否です。なぜなら一茶にとって辞世を詠むことは意味のない飾りごとであり、不自然なことだったのです。前もって辞世を用意するのは自らの死に際を飾り立てることであり、生きることを諦めることだと考えていたように見えます。一茶の65歳の人生は苦難の連続でした。
2度の脳梗塞、3歳のときに母を亡くす。“我と来て遊べや親のない雀” 27歳で芭蕉の「奥の細道をたどる旅に出ます。一茶が訪れたみちのくは、いまだ天明の大飢饉(1782-1788)の傷跡が残っていたと考えられ、容易な旅ではなかったと想像できます。“やせ蛙負けるな一茶これにあり” そして一茶は52歳にして28歳の菊と結婚します。そして溺愛していた娘さとを天然痘で亡くします。“露の世は露の世ながらさりながら” 私たちが生きている世界は、早朝草木の葉の上に結んでは消えていく露のように、はかないものであるとは重々承知しているけれども、そうであるとはいえ、辛いことである。生に執着すること、死を恐れることは煩悩であり、私たちおろかな人間は煩悩があればこそ、笑ったり、泣いたり、喜怒哀楽に翻弄されるもので、一茶はそのあるがままを受け入れて生きました。一茶には“老後”とか“余生”といった言葉は無縁でした。生きている最後の一瞬まで、煩悩にとらわれている愚かな人間の生を懸命に生き抜こうとしたのです。
私に話を戻します。私にとっても老後とか余生は今のところありません。この命が果てる最後の瞬間まで現役でいようと想っています。皆様に許して頂けるのであるならば。
小田和正さん率いるオフコースというバンドのヒット曲に「さよなら」があります。“もう終わりだね 君が小さく見える 僕は思わず君を抱きしめたくなる”
私は自分の命が愛おしい、最後の最後まで抱きしめて生きていたい、生きることに執着したいと改めて思うのです。今、ここで言います。だから皆様一度しかない命抱きしめていきましょう!
I will cling to my life as an active doctor till the last moment, if I would be allowed to do that by all of you.