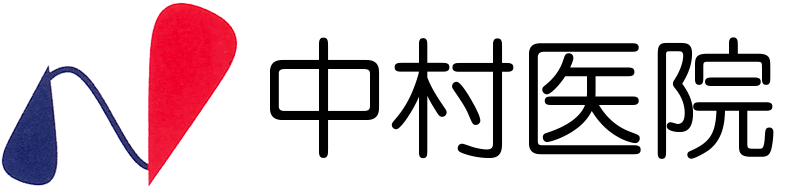ひとときという月間雑誌があります。創刊20周年特別企画で“わたしの20代”というものがありました。そこに作家、そして報道番組のキャスターでご活躍の阿川佐和子さんが書いておられます。20代とは生き方を見つけた時間だと。そして続きます。私の20代は暗かった。大学に入ってみたものの、極めたいものがあるわけじゃない。いずれ専制君主的な父とは違う、優しい人と結婚して家庭に入るのが身の丈にあった幸せと信じて就職はせず、専業主婦になったら自宅に工房を作ろうと。数打ってもお見合いはちっともまとまらず、先行きが見通せない時にTBSのプロデューサーから電話がかかり、フランスを取材し朝の生放送番組でレポートをすることになったそうです。
その後、報道番組のアシスタントに。でも政治も経済もわからなく、びーびー泣く毎日だったといいます。当時のプロデューサーに話したら「世の中みんなスペシャリストでも仕方がない。専門家と専門家を繋ぐ仕事があってもいいんじゃない」と言われ、嬉しくて泣けたそうです。
私の20代は医学部の学生で始まりました。医師になって人のお役に立ちたい、そんな崇高な思いを抱いていたわけでもなんでもなく、なんとなくブラックジャックが好きで外科医になったのです。入局したのが心臓・胸部・血管・消化器・小児と幅広い領域を手掛ける神戸大学第2外科でした。研修1年目は大学で脳以外のほぼ全ての臓器の手術に立ち会いました。
とりわけ私が心を惹かれたのが心臓外科でした。救急救命に命をかける心臓外科に進みたい、そんな私の希望を無残にも打ち砕いたのが同期7人の間で2年目の研修病院を選ぶくじ引きでした。心臓外科の病院としては、姫路循環器病センターがありましたが私ははずれ、甲南病院外科に行きました。3年目は当時の国立篠山病院外科と心臓外科とは無縁の病院に出張し(もちろん先輩の先生方には外科医としての一般的な技術は教えて下さり感謝しておりますが)、年々心臓外科医からは遠ざかっていく、自分としては方向性を見失っていく思いがしておりました。
そんな中、医学博士を取るための研究が始まりました。私が選んだテーマは和田心臓移植以来滞っていた心臓移植の研究でした。折しも日本全国で心臓移植再開の機運が高まっていた時です。それがもとで米国留学のチャンスを頂き、心臓外科医としての道筋がついたのです。折しも私がすでに30才に達した時でした。
さて、阿川佐和子さんに話を戻します。4才で視力を失った三宮真由子さんのエッセイ“鳥が教えてくれた空”から引用されています。鳥は神様の箸休めに違いない。鳥は非力で小さな存在かもしれないけど、もしもいなくなったら味気ない。三宮さんは鳥の存在と出会ったことにより感性が広がったとのことです。“光を失った私は、空を飛ぶ野鳥に世界の広さを教わった”阿川さんは、私もメインの料理を引き立てる小さな皿の箸休めみたいな人間になれたら。今はそんな気持ちでいます。と結んでおられます。
I want to be a person like Hashiyasume, such as a side dish served between the main course.
今から思えば私の20代は毎日どうにかなるさという思いで過ごしていたような気がします。